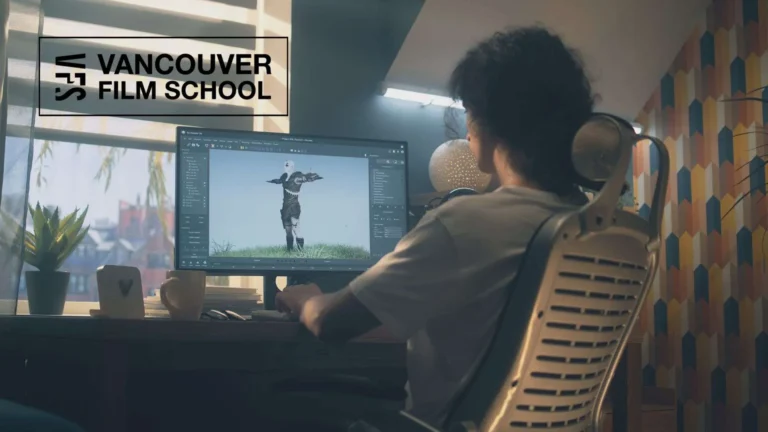Graphic and Visual Design Courseにdrawingのレッスン
以前のブログ「カナダ・Co-op留学で学ぶのはスキルだけではない」で、卒業後実際に仕事を始めた場合に重要となる心構え等を授業の中で教えてもらったということを書きました。
今回は、前回とは別の先生が授業の中で教えてくれたことや先生の気付きをご紹介します。
私の履修しているコースは二人の先生がトピックを手分けして教えてくれる構成になっています。今回の先生はアニメやストーリー・ボード(絵コンテに近いもので映像作品のカット割り等を描いて可視化したもの)を描いてきたプロフェッショナルです。Graphic Design Courseなのに、紙に鉛筆で描いたり、ペンでパッドを使ってデジタルに描いたりと、実際にdrawingする授業を採り入れているカレッジがどれほどあるのかわかりませんが、子供の頃から絵心皆無の私はdrawingのレッスンがあると知って恐々としていました。
どれほど絵心が皆無かというと、私が描くものの中で客観的にそれと判別可能なものは「ナナホシテントウムシ」だけ、小学校の美術の時間に鏡を見ながら描いた自画像が隣のクラスの男子そっくりだったという救いようの無さでした。絵を描くという行為が一種のトラウマになっていると先生に白状した私に「人物の顔が一番難しいのだから思うように描けなくても大丈夫。理論がわかれば描けるようになるよ。」と人の顔を描く際のグリッドの引き方などを丁寧に教えてくれました。理論立てて教えてもらうと描けるようになるものなのですね。
どうやっても上手く描けないので大嫌いだった立体物も、Vanishing Point(消失点)というものの設定とグリッドの引き方を教えてもらっただけで上手に描けるようになって自分でも驚きました。理論とやり方をきちんと教えてもらう、理解する、これだけで出来るようになるのです。Drawingももう恐くありません。
カナダ人の先生と留学生の文化的背景の違いからくる視線の着地点
広告デザインの練習でも多くのことを学びました。
「人の視線は一般的に左上から入って右下へ抜ける。その間に視線をどう誘導するかで効率が変わってくる。」のだそうです。左上にアイ・キャッチーな色や形を置き、視線を引き付ける流れが止まらないように文字や絵等を配置し、最終的に最も大切な売り文句や商品へと誘導するのだそうです。これはこれで重要な情報だと思います。
ところが、実は私は広告やポスター等を見る際に、まず中央を見てから視界を四方へ広げていく質なので、「左上から入る説」には驚きました。英語の文章は左から右へと流れますので、英語を母語とする人は左上から入る習慣が付いているのかもしれないと勝手に推測しています。日本語は縦書きと横書きの両方を使いますので視線の着地点と流れは多様性があるかもしれません。皆さんはまず最初にどこに視線を落としますか?
この「視線の最初の着地点」について討論していた時に、クラスメイトが「僕は左上というより絵や写真にまず視線をやります。英語が母語ではないので、文字を読みにいくより絵や写真で何の商品なのかを掴む方が早いからです。」と言いました。
これには私もすんなり同感しました。ところが先生がえらく驚いたのです。「そうか!私は英語が母語だから、まず文字情報を取ることから入るけれど、言われてみれば、母語でない人はそうなってもおかしくないね!素晴らしい気付きをもらったよ、ありがとう!」と展開していきました。先生も思えば同じ経験があったそうです。「そういえば仕事で数年台湾や韓国に住んだ時、漢字やハングルが読めない私は確かにまず絵や写真に視線をやって情報を取ろうとしていたな。すっかり忘れていたけれど、今の一言で思い出させてもらったよ。」と教える立場の先生も思わぬ気付きを得た授業となりました。
留学生同士でも文化の違いで様々なバリエーションが
また上記とは別に、先生の出すいくつかのお題(商品)を代表する色を使った広告を決められた時間内に制作するというquick exerciseがありました。
お題のうちの一つが「Money」でした。金融商品でも銀行の広告でもいいから、お金を代表するカラーを使いましょうというものです。
各人が制限時間内に制作した広告を全員で順番に見ながら感想を出し合います。ここはカナダですから、先生も学生もまずは褒め言葉から入ります。その上で改善点なども忌憚なく提案します。自分ではこれで良いと思っていても、他人の意見を聞くことで「なるほど、そんな手もあるな」という気付きになるから面白いものです。
さて、その「Money」の広告ですが、私以外のクラスメイトは皆「緑色」を使っていたのです。Money=緑?と驚きました。先生とクラスメイト達のイメージではMoneyはgreenとgoldなのだそうです。言われてみれば米ドル札は緑なので、今のカナダのようにカラフルなお札が普及する以前は、お札は緑色というのが一般的だったのかもしれません。
私は香港在住が長かったせいか、私の中でお金(お札)を代表する色は「黄色」なのです。1,000ドル札が黄色なので何の疑いも無かったのですが、クラスメイトがことごとく緑色を使っているのを見て、自分の刷り込みに気付いた次第です。本当に驚きました。
Colour is King!
別のquick exerciseでは、指定カラーであるblueとgreenとwhiteを使って、架空の会社「Canuck’s Wear」の看板を5枚制作しなさいというものでした。
なぜblueとgreenが指定カラーになるかわかりますね?そう、Canucksというのはバンクーバーのホッケー・チームで、チーム・カラーがblueとgreenなのです。色の濃淡などはCanucksのチーム・カラーのままでなくて良いけれど、三色のバランスを考えつつ調整しなさいというお題でした。
この練習で私が制作したうちの1枚をトップ画像にしてみました。先生が「一見してどんなウェアを売る会社かわかるし、blueとgreenのバランスがとても良い。黄色も入っているけれど目立たない薄い黄色なので、緑からの派生ということにしてあげる。この作品はポートフォリオに忘れずに入れなさい。」ととても気に入ってくれました。
そして先生が一連の授業で強調してくれたことが「Colour is King!」です。色の選び方やトーンが広告や商品、パッケージ等の良し悪しを大きく左右するということです。ターゲットとなる層や商品のグレードなどによって慎重に考えて色を選び調整することが大切だと私も授業を受けていく中で感じています。
これまで無意識に考えたり選択してきたものを再発見することが頻繁にあります。いくつになっても学びというのは楽しいものですね。
留学やバンクーバー生活についてのご質問などは下記のお問い合わせフォームへどうぞ!
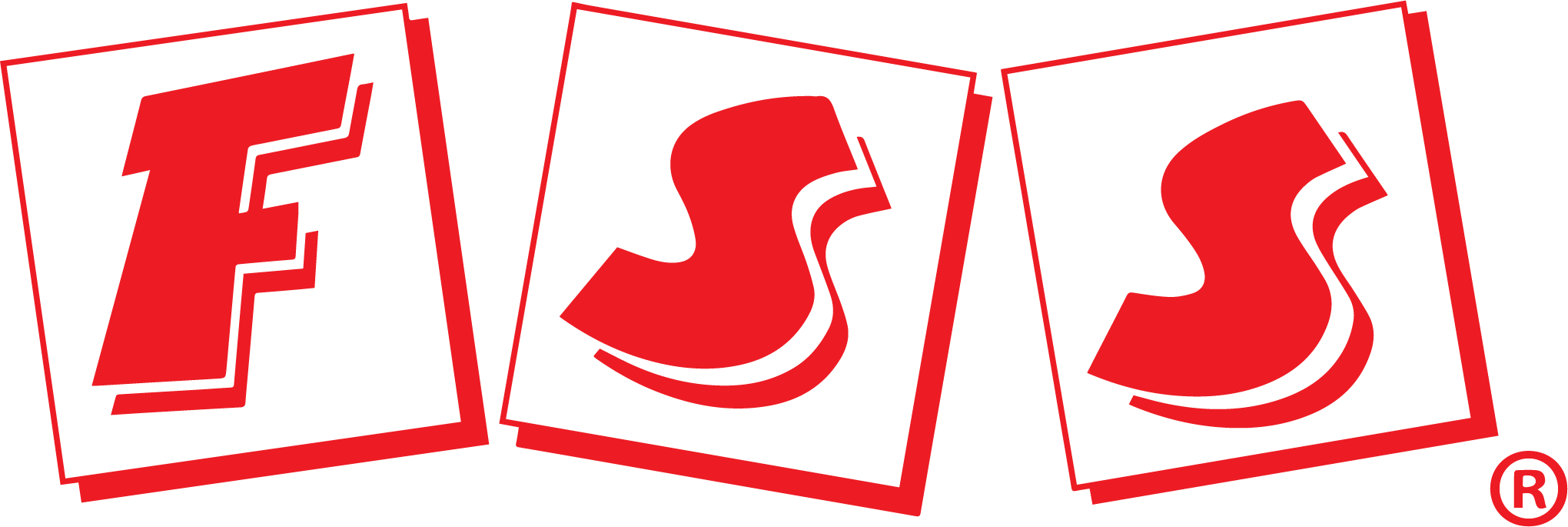










![from classroom crafts to kindness challenges embracing valentines day traditions in canada[1]](https://fsscanada.co.jp/wp-content/uploads/2024/02/From-Classroom-Crafts-to-Kindness-Challenges-Embracing-Valentines-Day-Traditions-in-Canada1-300x169.webp)